高額なパソコンやデスクなどを仕事用に購入したとき、「これってどうやって経費にするの?」と迷ったことはありませんか?
この記事では、個人事業主が知っておきたい減価償却の基本や計算方法について、仕訳の具体例とともにわかりやすく解説していきます。
減価償却とは?仕組みと目的を解説
減価償却(げんかしょうきゃく)とは、10万円以上の高額な備品を購入したときに一気に経費にせず、数年に分けて少しずつ経費にしていく方法です。
これは、長く使い続ける道具(パソコンやデスクなど)を購入した場合、その使う年数に合わせて費用を分けることで、毎年の利益ときちんと対応させるための仕組みです。
たとえば20万円のパソコンを購入し、耐用年数(たいようねんすう=使えるとされる年数)が4年とされている場合、毎年5万円ずつを経費として計上します。
減価償却の計算に必要な3要素|①取得価額②耐用年数③残存価額

減価償却を正しく行うには、押さえておくべきポイントが3つあります。
取得価額、耐用年数、残存価額――それぞれの意味や考え方を、順番に見ていきましょう。
①取得価額
減価償却の計算では、まず「取得価額(しゅとくかがく)」を正しく把握することが大切です。
たとえば10万円のデスクを購入し、組立費が5,000円かかった場合、取得価額は105,000円となります。
この金額をもとに、減価償却費を計算していくことになります。
②耐用年数
減価償却費の計算では「耐用年数(たいようねんすう)」がとても重要になります。
国が、資産の種類ごとに年数を定めており、たとえばパソコンなら4年、事務机なら15年といった具合です。
迷ったときは国税庁の「耐用年数表」を参考にすると安心ですよ。
③残存価額
減価償却の計算では、取得価額からこの残存価額を差し引いた金額をもとに、費用を按分していきます。
定額法で20万円の備品を4年で償却する場合、年5万円ずつ経費にできます。
定額法での減価償却計算法
減価償却にはいくつかの方法がありますが、個人事業主がよく使うのが「定額法(ていがくほう)」です。
これは、毎年同じ金額を経費として計上していくシンプルな計算方法です。
たとえば、取得価額が20万円で残存価額が0円、耐用年数が4年なら、毎年5万円ずつを経費にできます。
毎年減価償却する金額が一定なので、管理しやすいのが特徴です。
減価償却を初めて行う方でも取り入れやすい方法なので、まずはこの「定額法」から覚えておきましょう。
定率法の基本と計算方法
減価償却には「定率法(ていりつほう)」という方法もあります。
これは毎年一定の割合(率)で、帳簿上の価値を減らしていく計算方法です。
最初の年ほど大きな金額を経費にでき、年数が経つにつれて償却額が少しずつ減っていくのが特徴です。
パソコンやスマートフォンなど、数年で価値が下がりやすい道具に向いているともいえるため、こうした資産を早めに経費として計上したいときに便利な方法です。
翌年は、残りの帳簿価額10万円に0.5をかけて、5万円を償却します。
毎年の計算は少し複雑になりますが、償却率(しょうきゃくりつ)は国税庁の「減価償却資産の償却率表」に掲載されているので、確認しながら進めれば大丈夫。
初心者の方は、まず定額法からスタートして、慣れてきたら定率法の活用も検討するとよいでしょう。
備品購入時の月割計算

備品を購入した初年度は、取得した月によって、その年に計上できる経費の金額が変わります。
使い始めた月から年末までの「使用した月数」に応じて、経費を按分(あんぶん)して計算する必要があるためです。
年間の償却額を12(か月)で割って、実際に使った月数分だけをその年の経費として計上します。
この場合、その年に経費にできるのは「5万円 ÷ 12か月 × 6か月分=2万5,000円」となります。
7月〜12月の6か月分だけがその年の対象になる、ということですね。
こうした「月割計算(つきわりけいさん)」を知らずに1年分をまるごと計上してしまうと、帳簿にズレが出てしまうことも。
正確な経費処理のために、初年度は購入時期にも注意を払っておきましょう。
【実例】パソコンを定額法で減価償却するときの仕訳
例)2025年7月に20万円のパソコンを購入した。
国税庁の「耐用年数表」によると、耐用年数は4年であった。
< 購入初年度の減価償却 >
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
| 減価償却費 | 25,000 | 器具工具備品 | 25,000 | パソコン償却(2025年7月購入・定額法・6か月分) |
・取得価額:200,000円
・残存価額:0円
・耐用年数:4年
・購入月:7月(※7月〜12月の6か月使用)
(200,000円 − 0円) ÷ 4(年) × 6 (ヶ月)÷ 12(ヶ月)
= 50,000円 × 0.5
= 25,000円
個人事業主なら知っておきたい!一括償却資産と特例
減価償却と聞くと「何年も分けて処理するのが大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、一定の条件を満たせば、購入した年にまとめて経費にできる特例があります。
それが「一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)」と「少額減価償却資産の特例」です。
一括償却資産
取得価額が20万円未満の資産は、「一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)」として、3年間で均等に経費にすることができます。
耐用年数に関係なく、3年で割ればよいので計算もシンプルです。
少しずつ経費にしたいけど、複雑な計算は避けたい…という方にぴったりな方法です。
少額減価償却資産の特例
青色申告をしている個人事業主なら、「少額減価償却資産の特例(しょうがくげんかしょうきゃくしさんのとくれい)」を使うことで、30万円未満の資産をその年に全額経費にできます。
年間300万円までという上限はありますが、開業時など高額な出費が重なるタイミングでは特に活用価値が高い制度です。
「帳簿付けがしんどい…」そんなときはプロに頼ってみよう!
そんなときは、無理せずプロに頼るのも選択肢のひとつです。
✓ 初めての税理士探しに不安がある方には…
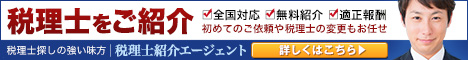
【税理士紹介エージェント】がおすすめ!
希望条件に合った税理士を、無料で紹介してもらえます。
仕訳に悩んだら、まずは担当税理士さんに相談してみましょう◎
✓ 記帳そのものを丸ごとお願いしたい方には…

【記帳代行お助けマン】が助けてくれます!
フリーランス、中小企業、税理士事務所に特化した記帳入力のアウトソーシング会社。
日々の記帳作業はプロにまかせて、事業に集中できる環境を整えましょう!
まとめ
高額な備品を購入したら「減価償却」を使って、数年にわたって経費として処理していく必要があります。
取得価額・耐用年数・残存価額の3つをしっかり押さえておけば、計算もスムーズに進められます。
個人事業主にとっては、償却方法や月割計算、一括償却や特例など、事業の状況や資金繰りに合った方法を選ぶことが大切です。
たとえば、開業初年度など出費が多い年は、特例を活用して早めに経費化するのも有効な選択肢になります。
なんとなくで処理してしまうと、あとから帳簿や申告で困ることも。
今回の内容を参考に、備品を購入するタイミングから計画的に減価償却を考えていきましょう。
ご自身の状況に合っているか不安な場合は、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
「自分に合った処理方法がわからない」「仕訳が合っているか心配…」という方は、記帳代行サービスでプロに任せてみるのもおすすめです!

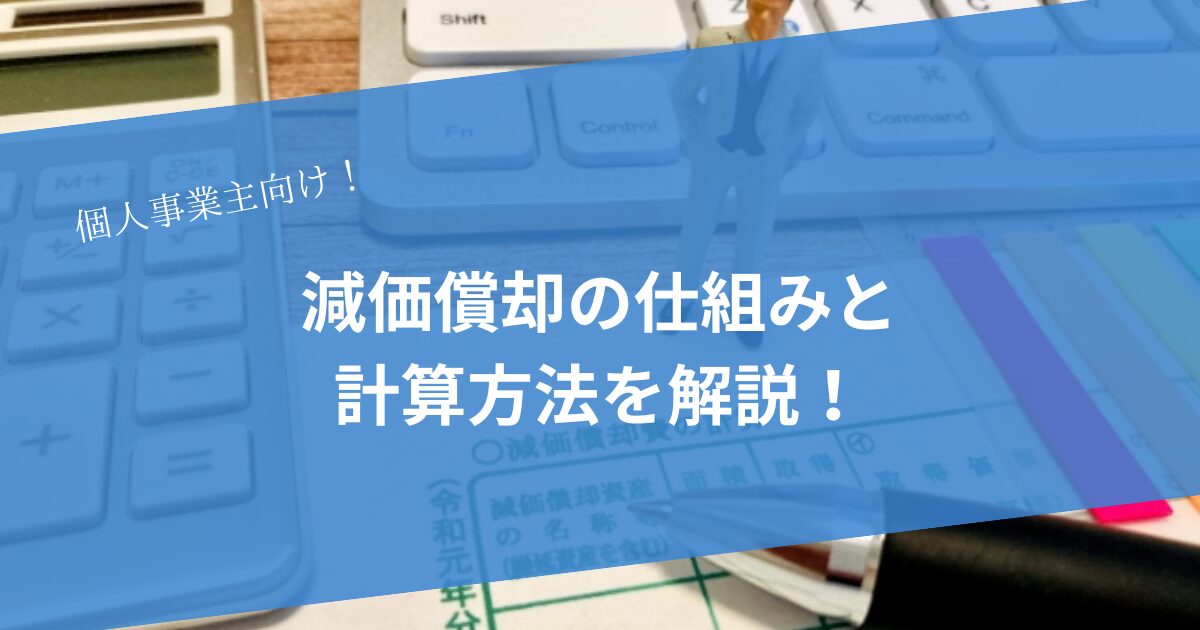



ちょっとした疑問も聞きづらくて、モヤモヤを抱えたまま進めることに…。
だからこそ、「いつでも相談できるパートナー」がそばにいると、本当に心強いです!
自分に合ったサポートを見つけて、安心して確定申告シーズンを迎えましょう◎