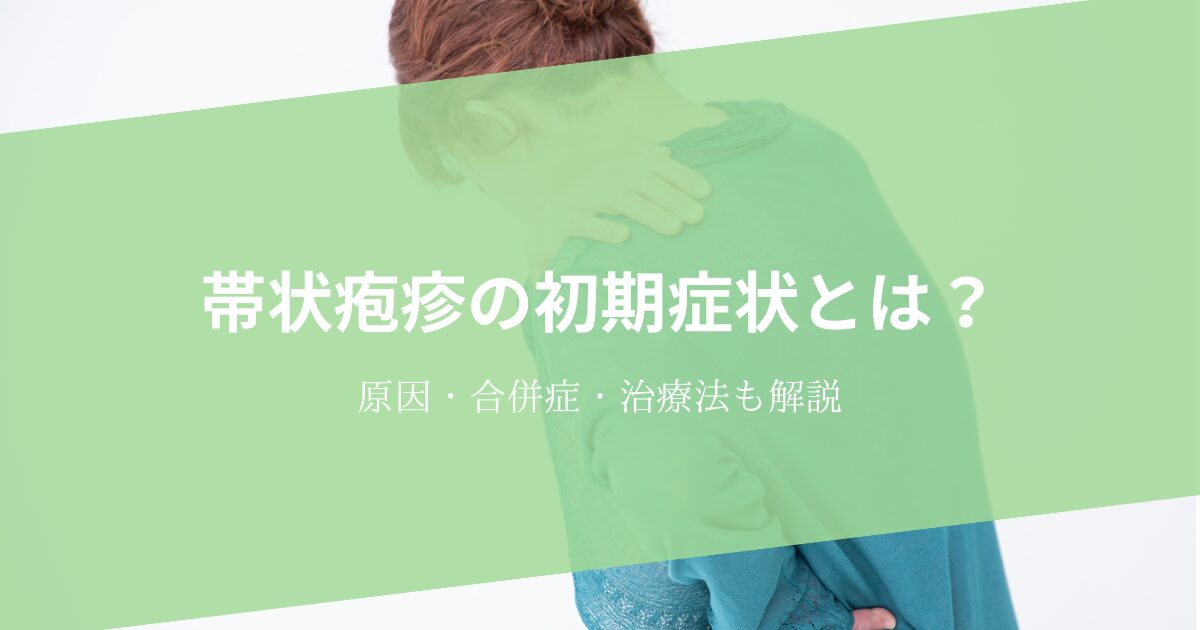帯状疱疹(たいじょうほうしん)は、過去に水ぼうそうを経験した人なら誰でも発症する可能性があります。
初期には、皮膚の違和感や痛みなどのサインがあらわれるのが特徴です。
本記事では、帯状疱疹の原因から主な症状、治療法、予防対策までをわかりやすく解説します。
帯状疱疹とは?
帯状疱疹とは、過去にかかった水ぼうそうのウイルスが再び活動することで、皮膚に痛みや発疹を引き起こす病気です。
このウイルスは水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルスと呼ばれ、体内の神経節(しんけいせつ)に潜んだまま、何年も経ってから再活性化します。
50代以上で免疫が低下している人や、強いストレスを感じている人が発症しやすい傾向にあります。
皮膚に帯のような水疱(すいほう)があらわれ、激しい痛みをともなうこともあります。
帯状疱疹の原因
帯状疱疹の主な原因は、水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化によるものです。
このウイルスは、水ぼうそうが治った後も神経節に潜んでおり、長い年月を経て免疫力が落ちたときに再び動き出します。
例えば加齢やストレス、過労、病気などが引き金となるケースが多くみられます。
また、50代以降に発症が増えるのも、免疫力の低下が関係しています。
ウイルスが再活性化する仕組みを知っておくことで、発症リスクを減らす意識づけに役立てられるでしょう。
帯状疱疹の発症リスクを高める要因
帯状疱疹は、ある条件が重なることで発症しやすくなります。
免疫力の低下のほか、年齢や生活習慣、持病の有無も影響します。
身近な原因を知ることが予防の第一歩です。
加齢による免疫力の低下
年齢とともに免疫機能は衰え、体の防御力が落ちていきます。
年齢を重ねる程リスクは高くなるため、日頃から予防意識を大切に過ごしましょう。
ストレスや過労
強いストレスや過労は、帯状疱疹の発症リスクを高める要因のひとつです。
精神的・肉体的な負担が続くと免疫力が下がり、水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化しやすくなります。
慢性疾患を患っている
糖尿病やがんなどの慢性疾患を抱えている人は、帯状疱疹を発症しやすい傾向があります。
これらの病気は免疫力を長期間にわたって低下させるため、水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化を招きやすくなるためです。
さらに、抗がん剤治療中の患者での発症例も多く報告されています。
持病がある方は、日常の体調管理がより重要になります。
帯状疱疹の症状と一般的な経過
帯状疱疹は初期の違和感から始まり、皮膚や神経に強い症状を引き起こします。
発疹や痛みの変化には一定の経過があるため、一般的な経過を知っておくことで、早期発見の手がかりにもなります。
初期症状(発症前〜数日)
皮膚の違和感
帯状疱疹の初期には、皮膚にかゆみやピリピリとした軽い痛みを感じることがあります。
これは、水痘・帯状疱疹ウイルスが神経を刺激するためです。
見た目に異常が出ていない段階で違和感が出ることも多く、早めに気付けば重症化を防ぐための対応が取りやすくなります。
感覚過敏
水痘・帯状疱疹ウイルスが神経を傷つけることで、皮膚に軽く触れるだけで強い刺激を感じる、感覚過敏がよくみられます。
衣服が当たるだけでヒリヒリしたり、寝返りを打つのがつらく感じたりすることもあります。
全身症状
帯状疱疹は皮膚の異常だけでなく、全身に症状があらわれることもあります。
ウイルスの再活性化によって免疫が刺激され、体全体が反応するためです。
具体的には微熱やだるさ、頭痛、関節の違和感などが出る場合があります。
皮膚症状(発症後数日〜1週間)
痛みを感じた部位に赤い斑点があらわれる
帯状疱疹を発症すると、はじめに痛みを感じた場所に赤い斑点があらわれます。
これは、水痘・帯状疱疹ウイルスが神経に沿って皮膚へと広がるためです。
皮膚の違和感に続いて赤みが出てきたら、早めの受診をおすすめします。
赤い斑点から小さな水疱に変化する
帯状疱疹の皮膚症状は、赤い斑点があらわれた後、数日で小さな水疱(すいほう)へと変化していきます。
水疱は透明またはやや濁った液体を含み、かゆみや痛みをともなうことも。
特徴的な見た目のため、この段階で診断されることも多く、早期受診と早期治療がポイントです。
水疱が破裂して痂皮(かさぶた)になる
帯状疱疹では、小さな水疱が数日で破れ、表面に痂皮(かひ/かさぶた)が形成されていきます。
これは、炎症を起こした皮膚が自然に治ろうとする反応によるものです。
かさぶたになると、かゆみや痛みをともなうことがありますが、無理に剝がすと跡が残る恐れがあります。
痛みの特徴
チクチク・ズキズキ・焼けつくような感覚など、痛みの種類は人によってさまざまです。
なかには軽い刺激でも激痛を感じることがあり、生活に支障をきたす場合もあります。
帯状疱疹で起こりうる合併症
帯状疱疹は皮膚症状だけでなく、重い合併症を引き起こすことがあります。
神経や目、耳、中枢神経にまで影響が及ぶこともあるため、早めの対応が重要です。
帯状疱疹後神経痛(PHN)
帯状疱疹が治った後も、痛みが長く続くことがあります。
これは帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれ、ウイルスが神経を傷つけた影響によるものです。
例えば、患部の皮膚に触れたり、服がこすれたりするだけで強い痛みを感じることもあります。
高齢になる程発症リスクが高まるため、初期段階での治療がとても重要です。
生活の質を保つためにも、早めの対策が欠かせません。
眼帯状疱疹
帯状疱疹が目のまわりに発症すると、眼帯状疱疹(がんたいじょうほうしん)と呼ばれる合併症を引き起こすことがあります。
水痘・帯状疱疹ウイルスが眼の神経に影響を及ぼすことで、結膜炎や角膜炎、視力低下を引き起こすリスクも。
ラムゼイ・ハント症候群(耳帯状疱疹)
帯状疱疹が耳のまわりに発症すると、ラムゼイ・ハント症候群(耳帯状疱疹)を引き起こすことがあります。
水痘・帯状疱疹ウイルスが顔面神経に感染することで、耳の痛みに加え、顔面のまひや聴力の低下、めまいがみられることもあります。
発見が遅れると後遺症が残る可能性があるため、早期治療がとても重要です。
中枢神経系の合併症
帯状疱疹が重症化すると、まれに中枢神経系(ちゅうすうしんけいけい)に影響を及ぼすことがあります。
水痘・帯状疱疹ウイルスが脳や脊髄に広がることで、髄膜炎(ずいまくえん)や脳炎などを引き起こすことがあるのです。
命に関わるケースもあるため、早期の判断がカギになります。
播種性帯状疱疹
帯状疱疹が重症化すると、播種性(はしゅせい)帯状疱疹に進行することがあります。
これは、水痘・帯状疱疹ウイルスが全身に広がり、水ぼうそうのような発疹が体の各所に出る状態です。
免疫力が著しく低下している人に多くみられる合併症で、内臓に影響が及ぶ危険もあります。
命に関わることもあるため、早期の診断と治療が必要不可欠です。
帯状疱疹の治療法
帯状疱疹は、早期治療によって重症化や合併症を防げる可能性があります。
ここでは、帯状疱疹に対して行われる一般的な治療法をご紹介します。
抗ウイルス薬の使用
帯状疱疹の治療には、抗ウイルス薬の使用が効果的です。
水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑えることで、症状の悪化や合併症の予防が期待できます。
代表的な薬は、アシクロビルやバラシクロビルなどです。
痛みの管理
帯状疱疹の治療では、痛みの管理も欠かせません。
ウイルスが神経に作用し、強い神経痛を引き起こすことがあるからです。
具体的には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や神経障害性疼痛(とうつう)に使われるプレガバリン、局所麻酔薬の貼付などが使われます。
痛みを我慢すると生活に支障をきたすため、症状に合わせた適切なケアが早期回復につながります。
中医学的アプローチ
補助的な治療法として、中医学を取り入れる方法もあります。
中医学とは、身体全体のバランスを整えることで、免疫機能の回復や痛みの軽減を目指す考え方です。
漢方薬や鍼灸(しんきゅう)によって、神経痛の緩和や睡眠の質が改善するケースもあります。
現代医療と併用することで、身体への負担を抑えながら回復をサポートできる可能性があります。
帯状疱疹の予防法とワクチンの効果
帯状疱疹の予防には、ワクチンの接種が有効とされています。
現在は50歳以上を対象に、発症や重症化を抑える効果が高いワクチンが複数登場し、注目を集めています。
接種を検討する際は事前にかかりつけ医と相談し、メリット・デメリットを理解したうえで決めましょう。
まとめ
帯状疱疹は、免疫力の低下をきっかけに、体内に潜んでいたウイルスが再活性化することで起こります。
初期症状の見極めが遅れると、強い痛みや合併症につながることもありますが、早期の受診と治療で重症化を防げます。
予防には生活習慣の見直しと、ワクチン接種が効果的です。
体に違和感を覚えたら我慢せず、早めにかかりつけの医療機関を受診しましょう。