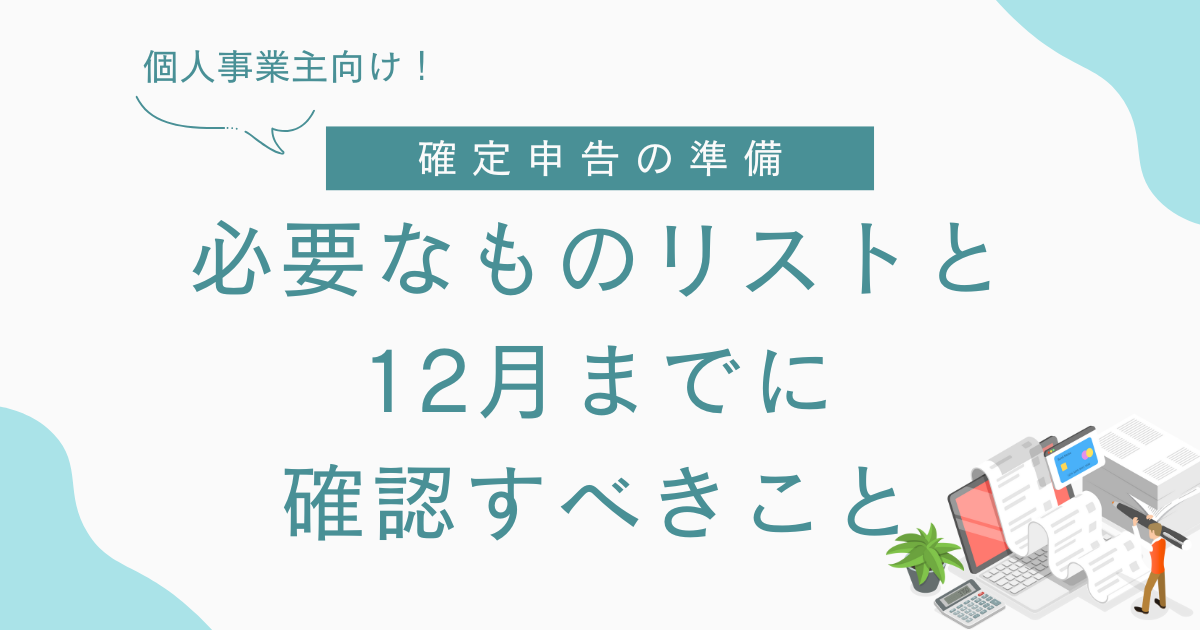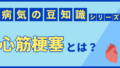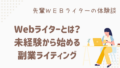確定申告は毎年2〜3月が提出期間ですが、10月~12月を目安に準備を始めておくと安心です。
税務署や国税庁、会計ソフトのサポートが混み合う前に、必要な書類や暗証番号を早めに確認しておきましょう。
確定申告に必要なもの一覧

確定申告には、身分証明や収入・経費・控除に関するさまざまな書類が必要です。
ここでは種類ごとに整理して紹介します。
本人確認に必要なもの
確定申告で最初に求められるのが本人確認書類です。
マイナンバーカードがあれば番号確認と身元確認を一度に済ませられるので便利ですね。
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カード(マイナンバーが記載された薄い紙のカード)か住民票の写しでマイナンバーを確認し、運転免許証やパスポートで身元を証明する必要があります。
顔写真付きの身分証明書がない方は、健康保険証と年金手帳など2点での確認が必要となります。
手元にあるか、事前に確認しておきましょう。
収入に関する書類の準備
個人事業主やフリーランスの場合、すべての収入を正確に申告する必要があります。
主な収入源となる取引先からの支払調書(源泉徴収票のようなもの)があれば参考になりますが、支払調書の交付義務は限定的なため、自分で売上を管理することが重要です。
請求書の控えや入金が確認できる通帳記録、クレジットカードの明細なども大切な証拠書類となります。
副業をしている方は、給与所得の源泉徴収票も忘れずに準備してください。
最近では電子請求書やオンライン決済も増えているため、デジタル形式の記録もプリントアウトするか、PDFで整理しておくと安心です。
経費の領収書や明細の整理
経費として計上できるものの領収書や明細を整理することで、所得税の節税につながります。
事業に関連する文房具代、通信費、家賃の一部、交通費などが対象となるため、これらの領収書やレシートは大切に保管してください。
最近は電子レシートやクレジットカードの明細も証拠書類として認められているため、紙の領収書がない場合でも心配ありません。
ただし、家事按分(プライベートと事業の按分)が必要な費用については、合理的な計算根拠を用意しておきましょう。
たとえば自宅兼事務所の家賃は、使用面積や使用時間で按分するのが一般的です。
領収書は月別や項目別に分けて保管しておくと、後々の整理が楽になりますよ◎
各種控除に必要な証明書
所得控除を受けるためには、それぞれの証明書が必要になります。
生命保険料控除では保険会社からの控除証明書、地震保険料控除では保険会社の証明書、社会保険料控除では国民年金保険料の控除証明書や健康保険料の納付済み通知書などが該当します。
医療費控除を受ける場合は、病院の領収書や薬局のレシートを保管しておきましょう。
年間10万円(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えた分が控除対象となります。
ふるさと納税をした方は、寄附金受領証明書が必要です。
これらの証明書は年末から年始にかけて郵送されることが多いため、紛失しないよう注意深く保管してください。
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo掛金など)の証明書も忘れがちなので、チェックリストを作っておくと安心ですね。
電子申告に必要な暗証番号とID
e-Taxで電子申告をする場合、マイナンバーカードや利用者識別番号など複数の暗証番号が必要です。
忘れると再発行に時間がかかるので、要注意です!
マイナンバーカード関連の暗証番号
マイナンバーカードには複数の暗証番号が設定されておりますが、e-Taxでは電子証明書用暗証番号(6桁〜16桁の英数字)が必要となります。
マイナンバーカード自体の有効期限も確認しておいてください。
有効期限が近い場合は、確定申告期間中に期限切れとならないよう、早めの更新手続きをおすすめします。
暗証番号がわからない場合は、お住まいの市区町村の窓口で再設定できますが、本人確認書類とマイナンバーカードが必要になります。
e-Taxログインに必要な番号と暗証番号
e-Taxを利用するには、利用者識別番号(16桁の番号)と暗証番号(8桁以上の英数字)が必要です。
初回登録時に自分で設定した番号のため、忘れてしまう方も少なくありません。
マイナンバーカード方式の場合は、マイナンバーカードの電子証明書用暗証番号でログインできるため、利用者識別番号は不要です。
ID・パスワード方式を選択する場合は、事前に税務署で本人確認を行い、IDとパスワードを発行してもらう必要があります。
どの方式を利用するかによって必要な情報が変わるため、自分がどの方法でe-Taxを利用するか明確にしておきましょう。
暗証番号を忘れたときの注意点
暗証番号やパスワードを忘れた場合の対処法を知っておくと、トラブル時にも慌てずに済みます。
e-Taxの利用者識別番号の暗証番号を忘れた場合は、オンラインで再設定が可能ですが、あらかじめ設定しておいた秘密の質問と答えを入力する必要があります。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合は、市区町村の窓口での手続きが必要で、混雑する時期には時間がかかることがあります。
私の知人も確定申告直前にマイナンバーカードの暗証番号を忘れて、市役所で長時間待ったという経験をしています。
このような事態を避けるため、暗証番号は安全な場所にメモしておくか、定期的に確認して忘れないようにしておくことが大切ですね。
年末年始は行政機関が休みになることも考慮して、早めの確認をおすすめします。
12月までにやっておくべき準備

年明けに慌てないためには、12月までに帳簿や経費、控除証明書を整理しておくことが大切です。
会計ソフトへの入力も済ませておきましょう。
帳簿入力や経費の整理は年内に
12月中に売上と経費の入力を完了させておけば、確定申告期間中の作業負担を大幅に軽減できます。
特に現金での支払いや小額の経費は、時間が経つと内容を忘れがちなので、月末や週末にまとめて入力する習慣をつけておくとよいでしょう。
領収書やレシートは月別にファイリングし、事業用とプライベート用を明確に分けておくのがおすすめです。
家事按分が必要な費用については、按分割合の根拠となる資料も一緒に保管してください。
年末に近づくにつれて取引先への請求書発行や支払いが集中するため、11月頃から意識的に整理を進めておくと安心です。
デジタル化も進めて、スマートフォンのアプリで領収書を撮影管理すると、紛失リスクも減らせますね。
控除証明書の保管と確認ポイント
各種控除証明書は10月から12月にかけて順次郵送されるため、届いたらすぐに専用のファイルで保管しましょう。
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料控除証明書など、それぞれ発行時期が異なるため、チェックリストを作成して漏れがないか確認することが大切です。
医療費控除を予定している場合は、病院の領収書や薬局のレシートを集計し、年間10万円を超えそうかどうか早めに計算しておきましょう。
ふるさと納税の寄附金受領証明書も重要な書類の一つです。
電子データで提供される証明書もあるため、プリントアウトするか、e-Taxで電子申告する場合はデータのまま保存しておいてください。
年末調整で処理できなかった控除についても、確定申告で処理できることを覚えておくとよいでしょう。
会計ソフトやe-Tax環境の準備
使用している会計ソフトが最新バージョンに更新されているか、年内に確認しておきましょう。
税制改正に伴う機能追加やバグ修正が含まれている可能性があるため、早めのアップデートが安心です。
また、e-Taxを利用予定の場合は、パソコンのOSやブラウザが推奨環境を満たしているかチェックしてください。
マイナンバーカードリーダーの動作確認や、ICカードリーダーライタのドライバー更新も忘れずに。
スマートフォンでのマイナンバーカード読み取りを予定している場合は、アプリの最新版をインストールし、実際に読み取り動作を試しておくことをおすすめします。
会計ソフトからe-Taxへのデータ連携機能がある場合は、連携方法を事前に確認し、テストデータで動作確認しておくと本番で慌てずに済みますよ。
税務署が混雑する前に確認したいこと

税務署への問い合わせは12月以降混雑しがちです。
控除や申告方式の確認など、疑問点はできるだけ10月・11月に解決しておきましょう。
青色申告と白色申告の違いを確認
青色申告と白色申告の違いを理解しておくことで、適切な申告方式を選択できます。
青色申告は複式簿記での記帳が必要ですが、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰越しといったメリットがあります。
また、白色申告は記帳が簡単な反面、控除額が少ないというデメリットも。
青色申告承認申請書の提出期限は原則として開業から2ヶ月以内、または青色申告を開始したい年の3月15日までとなっているため、来年から青色申告にしたい場合は早めの手続きが必要です。
自分の事業規模や経理能力にどちらが適しているか迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
控除の対象になるか迷う支出の相談
事業に関連する支出かプライベートな支出か判断に迷う場合は、税務署に確認しておくと安心です。
具体例としては自宅兼事務所の光熱費、事業用と私用を兼ねた車両費、研修やセミナー参加費などです。
書籍代や新聞代も、業務に関連していれば経費として認められる可能性があります。
電話相談も可能ですが、具体的な領収書や明細を持参して窓口で相談する方が、より詳細なアドバイスを受けられるでしょう。
判断に迷う支出はリストアップしておき、まとめて相談すると効率的ですね。
e-Taxの動作確認と暗証番号の確認
e-Taxシステムの動作確認は、確定申告期間が始まる前に済ませておくことが重要です。
国税庁のホームページにアクセスし、実際にログイン画面まで進めるか確認してみましょう。
マイナンバーカード方式を利用する場合は、ICカードリーダーライタでの読み取りやスマートフォンでの読み取りが正常に動作するかテストしてください。
暗証番号も実際に入力して確認しておき、間違いがないことを確かめておきましょう。
推奨ブラウザや必要なソフトウェアの情報も最新版をチェックし、必要に応じてアップデートを行ってください。
事前の動作確認により、申告期間中のトラブルを防げるため、12月中までの実施がおすすめです。
確定申告の準備で迷ったら専門家へ相談を

控除にできるかどうか判断が難しい支出や、青色・白色申告の違いに迷ったときは、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
会社経営者・個人事業主のためのQ&Aサイト【タチアゲ】なら、税理士や弁護士などの士業の先生に無料で質問でき、最短即日で回答がもらえますよ◎
まとめ|早めの準備で安心の確定申告

確定申告の準備は10月頃から始めておくと安心です。
2月からの申告期間を迎える頃には、書類や環境が整っていて余裕を持てますよ。
必要書類の整理や暗証番号の確認、会計ソフトへの入力を年内に済ませておけば、税務署やサポート窓口が混み合う前に疑問点を解決できるでしょう。
特に初めて確定申告をする方は、早めに取り組むことで制度への理解も深まり、スムーズな申告につながります。
計画的に準備して、落ち着いて申告に臨んでくださいね。
確定申告に必要なものチェックリスト
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード暗証番号(署名用・利用者証明用)
- 利用者識別番号と暗証番号(e-Tax用)
- 源泉徴収票(給与・副業収入がある人)
- 請求書・売上帳簿
- 経費の領収書・レシート
- 銀行通帳・クレジットカード明細
- 各種控除証明書(社会保険料・生命保険料・小規模企業共済など)
- ふるさと納税の受領証明書
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける人)