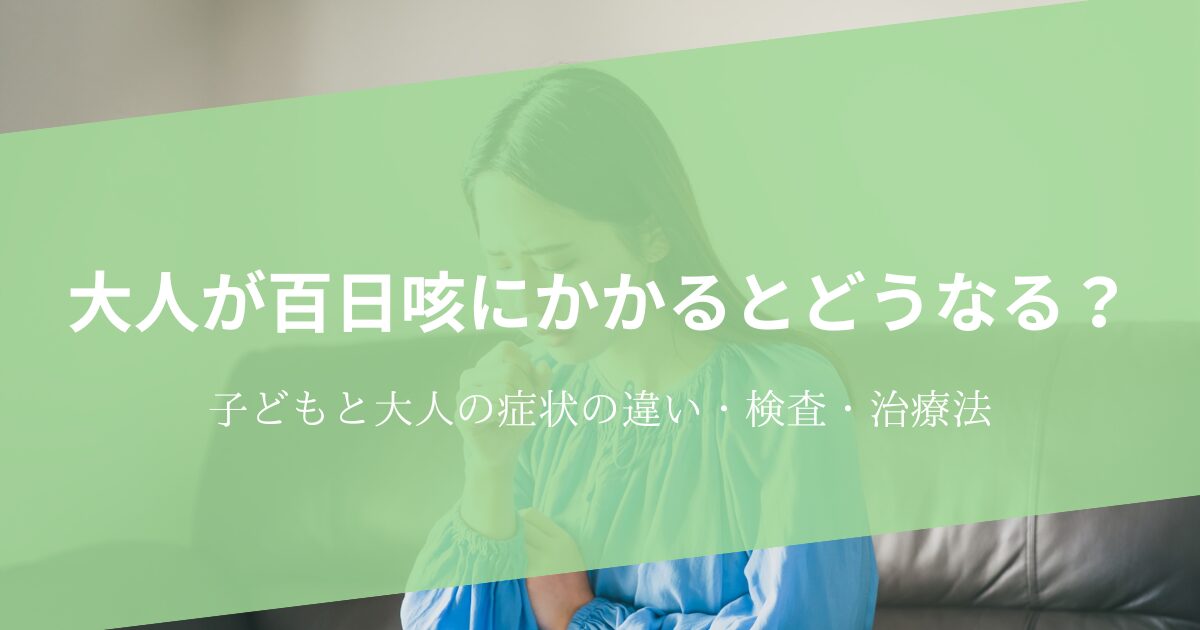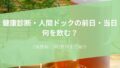百日咳(ひゃくにちぜき)の流行が全国で広がり、2025年7月17日現在、埼玉県内でも報告数が急増しています。
「子どもの病気」という印象が強いかもしれませんが、実は大人もかかる感染症です。
大人では風邪に似た症状のため見逃されやすく、気づかないうちに周囲にうつしてしまうこともあります。
この記事では、百日咳の症状や子どもとの違い、検査・治療のポイントをわかりやすく紹介します。
子どもたちの間で流行中!百日咳ってどんな病気?
百日咳は「100日続く咳」と表現されるほど、長引く咳が特徴の感染症で、特に子どもの間で流行しやすい病気です。
咳の際に飛び散るしぶき(飛沫)によって人にうつり、乳児では重症化しやすく肺炎や脳症を引き起こすことも。
今年(2025年)は流行が全国的に拡大しており、7月6日までの1週間で全国3578人に達しています。
発症初期は風邪のような軽い咳や鼻水がみられます。
徐々に連続した強い咳(けいれん性けいがい咳)に変わり、子どもでは息を吸うとき「ヒューッ」と音が出る(吸気性喘鳴 )のが特徴です。
乳児は母親からの免疫が十分でないため、感染しやすく、早期受診と予防がポイントになります。
百日咳の主な症状と特徴
百日咳は、風邪のような軽い症状から始まり、特徴的な咳へと進行します。
ここでは、百日咳の症状の流れを詳しく解説します。
カタル期
カタル期は百日咳の最初の段階で、風邪に似た症状が1〜2週間みられます。
鼻水やくしゃみ、軽い咳、微熱が中心で、特徴的な咳発作はまだ出ません。
痙咳期
痙咳期(けいがいき)では、百日咳の特徴的な症状があらわれます。
強く咳き込むため顔が赤くなったり、嘔吐したりすることもあります。
この時期はおよそ2〜3週間続きます。
回復期
回復期は、百日咳の症状が落ち着いてくる段階です。
この時期になると感染力はほとんどなくなります。
ただし、軽い咳が長引くケースもあり、完全に治るまでは数週間かかる場合も。
大人が感染するとどんな症状が出る?子どもとの違いは?
大人の百日咳は、子どもと比べて症状が目立たず気づきにくいことがあります。
感染を広げないためにも、症状の特徴をあらかじめ知っておくことが大切です。
乾いた咳が続き、なかなか治らない
風邪が治ったあとも咳だけが残り、数週間からときに数か月続くことも。
子どもに比べて「ヒューッ」という吸い込む音(吸気性喘鳴:きゅうきせいぜんめい)は出にくく、風邪や気管支炎と見分けがつきにくい点も特徴です。
高熱は出ず、微熱程度が多い
熱が目立たないぶん咳だけが長引き、風邪との違いに気づきにくいことが多いです。
咳以外の症状が少ない点も、大人特有の特徴です。
全身のだるさ、筋肉痛、頭痛などを伴う
長引く咳が続くことで、全身のだるさや筋肉痛が出やすくなります。
咳による体力消耗が原因で、頭痛や頭が重い感じ(頭重感:ずじゅうかん)がみられることも。
これらの症状は、咳が強く長引くほど目立ちやすいのが特徴です。
大人の長引く咳の見分け方と受診の目安
大人の百日咳は、乾いた咳が長く続くのが特徴で、風邪と見分けがつきにくい点も特徴のひとつです。
・2週間以上、咳が止まらない
・夜間や明け方に咳が強くなる
・咳のあとに嘔吐することがある
・周囲に同じような咳をしている人がいる
・職場や、子どもが通う保育施設で百日咳が流行っている
これらに当てはまる場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
百日咳の検査方法は?
百日咳を診断する際は、症状の出方や経過に応じて検査が行われます。
主な検査方法は、次のとおりです。
・培養検査:鼻やのどから菌を培養し確認する方法、結果まで数日かかる
・血清抗体検査:発症から2週間以上経った場合に役立つ
・抗原検査:短時間で結果が出るが、精度はやや低め
問診や診察、検査の結果を参考に診断が行われます。
大人の百日咳に対する治療法
百日咳の治療には抗生物質や対症療法などがあり、症状や体調に合わせて進められます。
抗生物質による治療
大人の百日咳では、抗生物質による治療が基本です。
主にマクロライド系の薬が使用され、服用期間が短く、副作用が比較的少ない点が特徴です。
発症初期に服用することで、感染を広げるリスクを抑える効果が期待できます。
対症療法
対症療法(たいしょうりょうほう)は、つらい咳などの症状をやわらげることが目的です。
- 休養と十分な睡眠
- こまめな水分補給
- 加湿
- 気管支拡張薬の処方(必要に応じて)
重症例や合併症リスクが高いときは入院も検討
大人が感染した場合でも、重症化した場合や合併症が疑われるときには、入院が必要になることがあります。
具体的には、呼吸困難が強い場合や脱水症状があるとき、基礎疾患を抱える人などが該当します。
百日咳を防ぐワクチン接種と追加接種の必要性
百日咳を防ぐには、ワクチン接種が重要です。
乳児は重症化しやすく、大人が知らないうちに感染源になってしまうことも。
日本では5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)を生後2か月から接種しますが、時間がたつと免疫が弱まってしまいます。
そのため大人でも、抗体が少なくなると再び感染するリスクがあり、追加接種(ブースター接種)がすすめられています。
乳幼児と接する機会が多い人や医療の現場で働く人には、特に意識してほしいポイントです。
まとめ
百日咳は大人もかかることがあり、乾いた咳が長く続くのが特徴です。
初めは風邪に似た症状のため見過ごしやすく、知らないうちに周囲にうつしてしまうことも。
特に乳児は重症化しやすいので、周囲の大人が感染源にならないことが大切です。
気になる症状があれば早めに医療機関を受診し、必要に応じて検査を受けることをおすすめします。
また、大人も状況に応じてワクチンの追加接種を受けることで、自分だけでなく周囲の人を守ることができます。
正しい知識をもって、日頃から予防を心がけましょう。