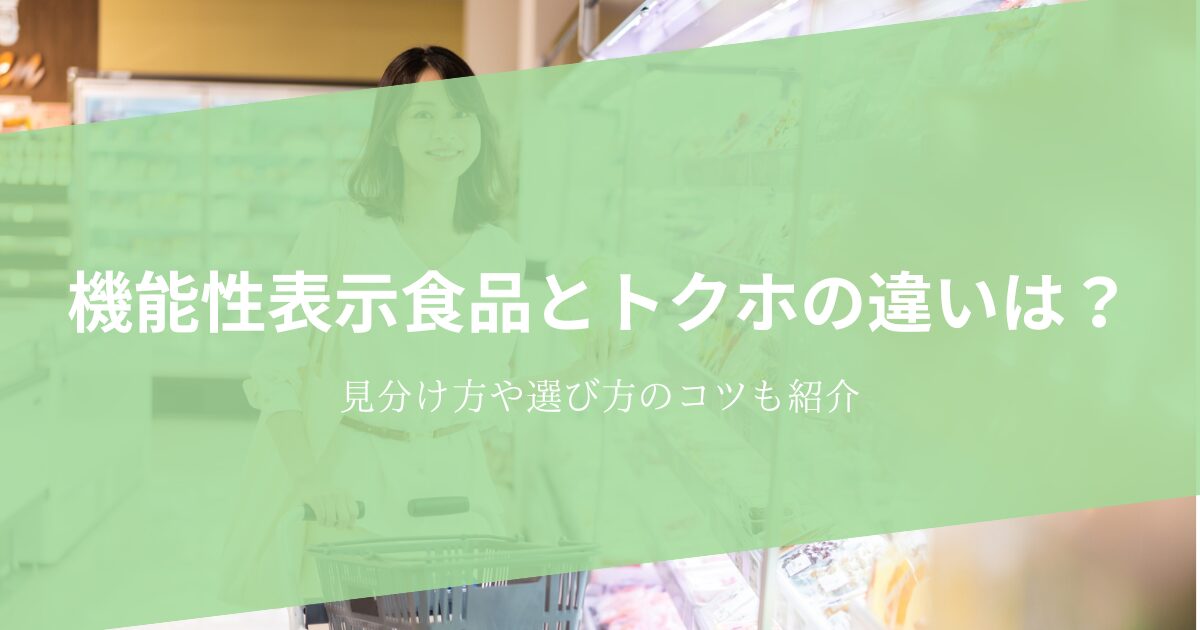健康志向の高まりとともに注目される「機能性表示食品」と「トクホ(特定保健用食品)」。
本記事では、両者の違いや見分け方、目的に合った選び方のコツ、活用のポイントまでをわかりやすく解説します。
賢く取り入れて、日々の健康づくりに役立てましょう。
機能性表示食品とは?
企業が消費者庁にエビデンス(科学的根拠)などの情報を届け出ることで、「お腹の調子を整える」「血圧を下げるのを助ける」などの機能性をラベルに明記することが認められています。
ただし、機能性表示食品は国による個別審査を受けているわけではなく、事業者の責任で販売されているのが大きな特徴です。
そのため、購入前には商品の成分や届出情報をしっかり確認することが大切です。
トクホや栄養機能食品と混同しやすい制度ではありますが、それぞれに違いがあるため、次の章で詳しく比較していきましょう。
機能性表示食品とトクホ(特定保健用食品)との違いは?
「機能性表示食品」と「トクホ(特定保健用食品)」は、どちらも健康維持に役立つ機能を表示できる食品ですが、制度の仕組みや表示方法には明確な違いがあります。
国の審査があるかどうか
トクホは、消費者庁が科学的根拠や安全性を審査・許可した食品です。
一方で、機能性表示食品は企業が独自に科学的根拠を示し、国へ「届出」をする制度で、国の個別審査は行われません。
表示のしかた
トクホは「特定保健用食品」のマーク(通称:トクホマーク)がパッケージに表示されますが、機能性表示食品にはそのようなマークはなく、「機能性表示食品」と文字で記載されています。
販売までの手続き
トクホは審査に数年かかる場合もあり、開発コストが高くなりがちです。
そのため商品価格も高めの傾向があります。
対して機能性表示食品は比較的短期間・低コストで届出できるため、ラインナップが豊富で手に取りやすい価格の商品も多く見られます。
根拠の公開方法
機能性表示食品は、届出された情報(成分の働きや試験内容)が消費者庁のWebサイトで公開されています。
自分で情報を確認して、信頼できる商品を選ぶことが求められます。
このように、トクホは国の審査による「お墨付き」がある一方で、機能性表示食品はより身近で手に取りやすいのが特徴です。
それぞれの特徴を理解して、目的に合った商品を選びましょう。
栄養機能食品との違いもチェック!
機能性表示食品とよく似た存在として、「栄養機能食品」もありますが、両者には明確な違いがあります。
栄養機能食品は、不足しがちな栄養成分(ビタミンやミネラルなど)を補うことを目的とした食品で、国が定めた基準を満たしていれば、企業は審査なしで販売できます。
「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」といった文言がパッケージに書かれている商品が該当します。
一方、機能性表示食品は、特定の成分が体の機能にどう作用するかを、科学的根拠を示したうえで届け出が必要です。
表示できる内容や根拠の扱いが異なるため、目的に応じて使い分けることが大切です。
機能性表示食品のメリットとデメリット
手軽に健康を意識できる機能性表示食品にも、実は注意したい点があります。
特徴を正しく理解して選びましょう。
機能性表示食品のメリット
機能性表示食品は、目的に合った商品を選びやすく、手軽に健康をサポートできる点が魅力です。
「脂肪の吸収を抑える」「睡眠の質を改善する」など、具体的な機能がパッケージに記載されています。
機能性表示食品のデメリット
届出番号や科学的根拠は消費者庁のサイトで確認できますが、内容が専門的でわかりにくいこともあります。
また、トクホのような共通マークがなく、商品によって表示の仕方が異なる点にも注意が必要です。
購入時は成分や表示内容をよく確認しましょう。
機能性表示食品の見分け方
店頭で見かける機能性表示食品は、表示を見れば見分けられます。
購入前にチェックすべきポイントを確認しましょう。
パッケージに「機能性表示食品」と明記されているか
まず、商品のパッケージに「機能性表示食品」と書かれているかどうかが、見分けるための大きな手がかりになります。
これは制度に基づいた正式な表示で、任意のキャッチコピーとは異なります。
多くの場合、パッケージの表面または裏面に表示されているので、購入前に確認しましょう。
「届出番号」が記載されているか
パッケージに「届出番号」が記載されていることも、機能性表示食品を見分けるポイントの一つです。
届出番号とは、企業が消費者庁に届け出た証拠として付けられる番号で、信頼性を確かめる手がかりになります。
実際の届出内容は、消費者庁の公式サイトで誰でも確認できるため、気になる商品があればチェックしてみましょう。
「○○成分が△△に役立つ」といった表現が使われているか
機能性表示食品には、「○○成分が△△に役立つ」といった具体的な機能を示す表現が記載されています。
これは科学的根拠に基づいて届け出された内容に沿っており、商品の特長を知るうえで重要な情報です。
「GABA(ギャバ)が血圧を下げるのを助ける」などの文言が代表例です。
表示内容を確認すれば、自分の目的に合った商品かどうかを判断しやすくなります。
「消費者庁長官の個別審査を受けたものではありません」と記載されているか
機能性表示食品には、「消費者庁長官の個別審査を受けたものではありません」という文言が表示されていることがあります。
これは国の審査を経ていないことを示すもので、トクホとの大きな違いです。
機能性表示食品とトクホ、どちらを選ぶ?
健康食品を選ぶ際は、目的や重視したいポイントに応じて使い分けることが大切です。
それぞれの特徴をみていきましょう。
エビデンス(科学的根拠)の信頼性を重視するなら「トクホ」
効果や安全性の信頼性を重視するなら、トクホ(特定保健用食品)がおすすめです。
国が審査を行い、科学的根拠に基づいて許可されているため、安心感があります。
例えば「お腹の調子を整える」と表示された乳酸菌飲料などは、その効果が評価されたうえで販売されています。
健康効果をしっかり期待したい人にとって、選択肢の一つになるでしょう。
自分の健康状態や目的に合った成分で選ぶなら「機能性表示食品」
目的に合わせて成分を選びたい人には、機能性表示食品が向いています。
さまざまな機能を持つ成分が使われており、自分の体調や悩みに応じて選べるのが特徴です。
「GABA(ギャバ)で睡眠の質を高めたい」「難消化性デキストリンで血糖値対策をしたい」など、目的がはっきりしていれば選択肢が広がります。
ライフスタイルに合わせて取り入れやすいのも魅力の一つです。
手軽に試してみたいなら「機能性表示食品」
「まずは気軽に始めてみたい」という人には、機能性表示食品がぴったりです。
トクホよりも価格が手頃で、スーパーやコンビニなどで簡単に購入できます。
血糖値や整腸などをうたった飲料やスナックなども多く、手軽に取り入れやすいのが特徴です。
毎日続けやすいことは、健康習慣を始めるうえでも大きなメリットになります。
機能性表示食品を活用する際のポイント
機能性表示食品をうまく取り入れるには、いくつかのコツがあります。
選び方や続け方のポイントを押さえておきましょう。
すぐに効果が出るわけではない
機能性表示食品は薬ではないため、短期間で劇的な変化を期待するものではありません。
焦らず、日常の食生活のなかで無理なく続けていくことがポイントです。
表示されている「届出番号」や「科学的根拠」は確認可能か
これは企業が提出した研究結果や成分の作用に関する情報で、商品の信頼性を見極めるうえで参考になります。
具体的には機能性や対象者、摂取目安量などが記載されており、購入前の判断材料になります。
気になる商品は、一度調べてみましょう。
配合成分が自分の健康状態に合っているか確認する
機能性表示食品を選ぶ際は、配合されている成分が自分の体に合っているかどうかを確認しましょう。
例えば、血圧に関わる成分を含む商品は、高血圧治療中の人に注意が必要です。
不安があるときは、かかりつけの医師や薬剤師に相談し、安全に取り入れることが大切です。
過剰摂取にならないように注意
成分によっては過剰摂取が体調不良の原因になることもあります。
複数の商品に同じ成分が含まれている場合、意図せず摂取量が増えてしまうことがあります。
1日の摂取目安量を守ることが大切です。
気付かぬうちに摂り過ぎていないか、日常的に意識しておきましょう。
「健康食品」や「サプリ」と混同しないようにする
機能性表示食品は、いわゆる健康食品やサプリメントとは異なる制度に基づいて販売されています。
効果をうたうだけのサプリと違い、表示内容に一定のルールがあります。
まとめ
機能性表示食品やトクホ(特定保健用食品)は、それぞれ異なる制度に基づいて販売されており、選ぶ際は表示や成分の特徴を見極めることが大切です。
安心して活用するには、「何を目的に取り入れるのか」を明確にし、自分の体調や生活スタイルに合ったものを選びましょう。
表示内容や届出番号を確認する習慣を持てば、情報に惑わされることなく、自信を持って選択できます。
まずは一つの商品から、表示を意識してチェックしてみてください。
参考文献
https://www.caa.go.jp/notice/assets/150810_1.pdf