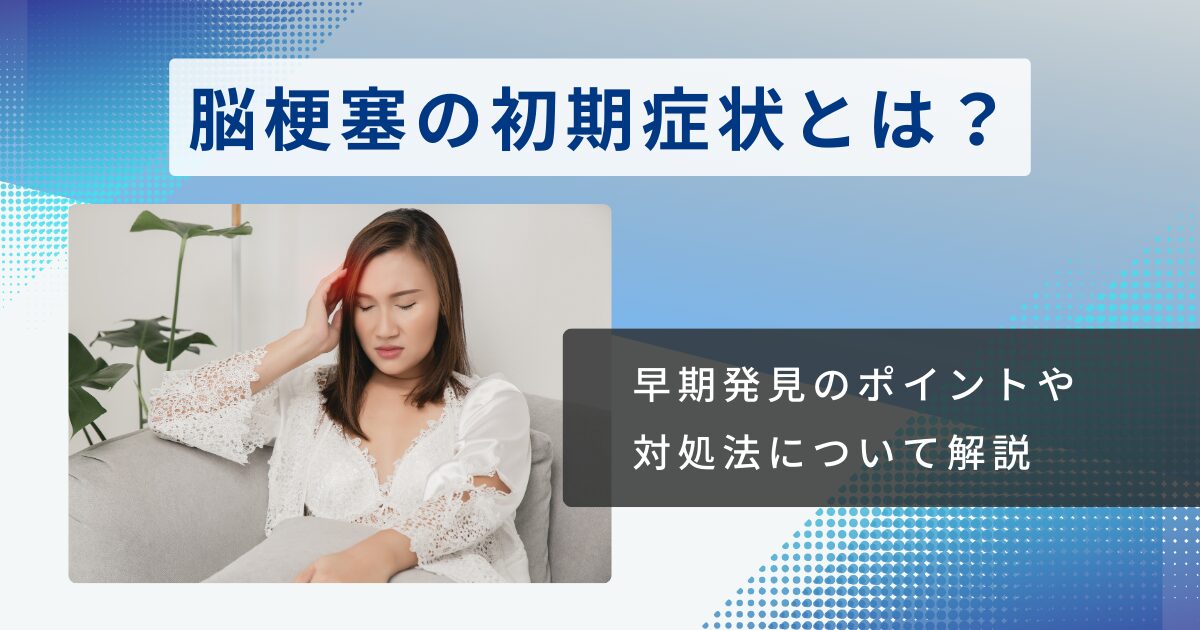「突然、言葉が出なくなった」「片方の手足に力が入らない」──そんな異変は、もしかすると脳梗塞のサインかもしれません。
脳梗塞は発症からの時間との勝負で、早期発見と迅速な対応がその後の回復に大きく影響します。
この記事では、脳梗塞の代表的な初期症状や、家庭でもできるチェック方法、万が一のときの対応の流れまでをわかりやすく解説します。
大切な命を守るために、今こそ知っておきたい知識です。
脳梗塞とは?
脳梗塞は、脳の血管が詰まり、血流が途絶えることで脳の細胞がダメージを受ける病気です。
脳は常に酸素と栄養を必要とするため、血流が止まると短時間で重大な障害が残るおそれがあり、早期発見・早期治療が重要です。
具体的には、脳の血流が数分間止まるだけで、手足の麻痺や言語障害などがあらわれることがあります。
脳梗塞の初期症状とは?
脳梗塞は症状が急激にあらわれることが多く、迅速な対応が重要です。
ここでは、脳梗塞初期に起こりうる症状について詳しく解説します。
突然の強い頭痛
これは脳の血流が一部で遮断され、周囲の神経に異常な刺激が加わるためです。
「バットで殴られたような痛み」「急に頭を締めつけられる感覚」と表現されることもあり、日常的な頭痛とは明らかに違います。
顔の歪み
脳梗塞の初期症状のひとつに、顔の左右のバランスが崩れることがあります。
脳の一部がうまくはたらかなくなり、顔の筋肉の動きが片側だけ弱くなるためです。
笑ったときに片方の口角だけが上がらない、まぶたが閉じにくいといった変化がみられます。
普段通りの表情が作れないと感じたら、すぐに医療機関へ相談しましょう。
言葉のもつれ・言葉が出ない
脳梗塞の初期には、うまく言葉が出てこなかったり、発音が不明瞭になることがあります。
これは、言語をつかさどる脳の部位に血流障害が起きるためです。
「こんにちは」と言おうとしても、「こ…んにゃちわ」となったり、意味の通らない言葉を口にしてしまうことがあります。
本人は話しているつもりでも、まわりが聞き取れないケースも少なくありません。
このような異変が見られたら、ただちに救急車を呼ぶことが重要です。
片側の手足のしびれや麻痺
脳の血流が一部で途絶えると、その部位がつかさどる手足の感覚や動きがうまくコントロールできなくなります。
具体的には、片方の手でコップが持てなくなる、片足がもつれて歩きにくくなるといった症状が起こることがあります。
一時的におさまっても安心せず、すぐに医療機関を受診することが大切です。
視力の異常
脳梗塞の初期には、突然片方の目だけが見えにくくなったり、視界がぼやけたりすることがあります。
これは視覚をつかさどる脳の部位に障害が起きることで、目自体に異常がなくても見え方に変化が出るためです。
「視界の半分が欠ける」「物が二重に見える」といった症状があらわれることがあります。
加齢による見えにくさとは異なり、急激な変化が特徴です。
めまい・ふらつき
ふらつきや平衡感覚の乱れも、脳梗塞の初期に見られる症状のひとつです。
脳の中でも体のバランスを調整する部位に異常が起きると、姿勢を保つことが難しくなります。
急に立っていられなくなったり、まっすぐ歩けなくなるケースもあります。
めまいや転倒が突然起こった場合は、「疲れ」や「立ちくらみ」などと決めつけず、早めに医療機関を受診しましょう。
意識障害や混乱
脳梗塞の初期には、意識がもうろうとしたり、急に言動がちぐはぐになることがあります。
これは脳のはたらきが一時的に低下し、思考や判断が正常に行えなくなるためです。
呼びかけに反応しなかったり、今いる場所や時間がわからなくなるなど、混乱した様子を見せることがあります。
「なんだか様子がおかしい」と感じたら、すぐに救急車を呼ぶ判断が重要です。
脳梗塞の早期発見に役立つ簡単なチェック方法
脳梗塞かどうかをすばやく見分けるには、いくつかの簡単な確認方法があります。
「顔が左右対称に動くか」「両腕を同じ高さで保てるか」「言葉がはっきりしているか」などをチェックしましょう。
ここでは、チェック方法のひとつである「FASTテスト」について解説します。
FASTテストとは、脳梗塞を早期に発見するための4つのチェックポイントのことです。
次のような観察を行うことで、救急搬送が必要かどうかを判断しやすくなります。
- F(Face:顔)笑顔をつくってもらい、口元が左右対称かどうかを確認します。片方の口角が下がっていたり、表情がゆがんでいる場合は要注意です。
- A(Arms:腕)両腕を前に出して、手のひらを上に向けたまま10秒ほどキープできるかを見ます。どちらかの腕が下がってしまったり、うまく上げられない場合は異常のサインです。
- S(Speech:言葉)簡単な言葉や文章を繰り返してもらい、発音がはっきりしているかを確認します。ろれつが回らない、言葉が出てこない、意味の通らない話し方になっているときは注意が必要です。
- T(Time:時間)上記のいずれかに当てはまる症状が見られた場合は、すぐに119番通報を。「いつ症状が出たか」も伝えられるよう、時間を記録しておきましょう。
この4項目は誰でもすぐに確認でき、医療機関への連絡の判断材料になります。「あれ?」と思ったら迷わず行動することが大切です。
初期症状が現れた場合の緊急対応と医療機関への連絡方法
脳梗塞が疑われる症状に気づいたら、ためらわずに119番へ連絡することが最優先です。
脳の細胞は、血流が止まると数分でダメージを受けはじめ、時間が経つほど後遺症のリスクが高まります。
例えば、顔のゆがみや言葉のもつれ、片側のしびれなどが突然現れた場合、すぐに救急車を呼び、症状が出た「時刻」を正確に伝えましょう。
病院へ向かう際、自己判断で車を運転したり、様子を見るのは避けてください。
迅速な対応こそが、命を守るカギになります。
まとめ
脳梗塞は、初期症状を見逃さずに行動できるかどうかで、生命維持や後遺症の有無・程度が大きく変わります。
突然の頭痛や顔のゆがみ、ろれつの回らなさなど、いつもと違うサインがみられたときは、すぐに「FASTテスト」で確認を。
少しでも異変を感じたら、迷わず119番に通報することが大切です。
万が一に備えて、家族や身近な人と一緒に症状や対応方法を共有しておくと安心につながります。
いざという時に落ち着いて行動できるよう、正しい知識を持っておくことが何よりの備えです。
参考文献