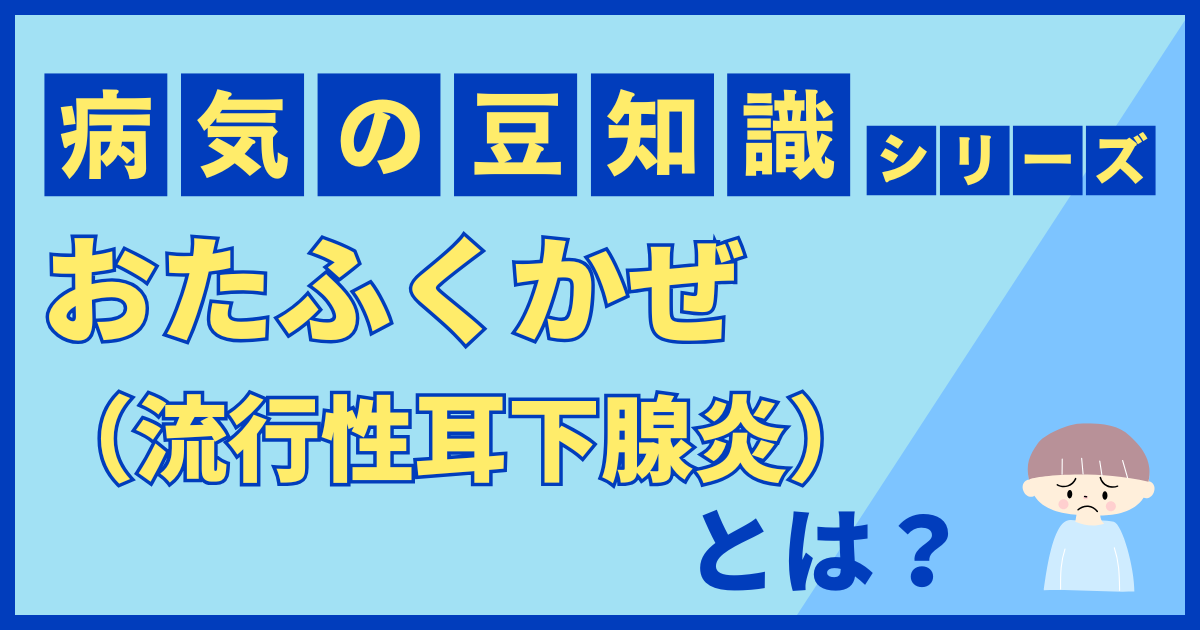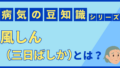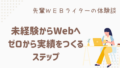おたふくかぜは、子どもがかかる病気の代表格として知られています。
ほとんどの場合は自然に治りますが、合併症を起こすこともあり油断はできません。
家庭内や学校で広がりやすい病気だからこそ、予防や早期対応が大切です。
概要
おたふくかぜは、ムンプスウイルスによって起こる感染症です。
- 主に飛沫(ひまつ)感染や接触でうつる
- 潜伏期間は2〜3週間とやや長い
- 学校や家庭など、集団生活の場で流行しやすい
一度感染すると免疫がつき、再びかかることはほとんどありません。
主な症状
最も特徴的なのは耳の下の腫れです。
- 耳下腺(じかせん)が腫れて痛みが出る
- 発熱(38度前後が多い)
- 咀嚼(そしゃく)や飲み込み時の痛み
- 倦怠感や頭痛
通常は1週間程度で腫れが引きますが、合併症として髄膜炎(ずいまくえん)や精巣炎(せいそうえん)、難聴などが起こることもあります。
主な治療法
おたふくかぜに有効な特効薬はありません。
治療は症状を和らげることが中心です。
- 発熱時には安静にして水分をこまめにとる
- 痛みが強い場合は解熱鎮痛薬を使用
- 食事はやわらかく消化の良いものを選ぶ
合併症が疑われる場合は、早めに医療機関で精密な検査や治療を受けることが大切です。
予防・セルフケア
最も効果的な予防法はワクチン接種です。
- ムンプスワクチンを2回接種することで高い予防効果が得られる
- 感染した場合は、他の人にうつさないよう学校や仕事を休む
- 家族内での感染を防ぐため、マスクや手洗いを徹底する
- 栄養と休養を意識して免疫力を保つ
予防接種と基本的な生活習慣で、流行を抑えることができます。
まとめ
おたふくかぜは自然に治ることが多い病気ですが、合併症を考えると油断できません。
特効薬がないため、ワクチンでの予防が最も確実です。
家庭や学校での感染拡大を防ぐためにも、日頃からの対策を心がけていきましょう。