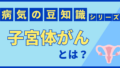タレントの山瀬まみさんが、約7か月の休養を経てラジオ番組に復帰しました。
休養の理由は、子宮体がんの手術を受けていたためだと明かされています。
さらに、がんの合併症によって脳梗塞を発症し、一時は集中治療室で治療を受けていたことも公表しました。
この報道を受けて、「そもそも子宮体がんとは何か」「どうして40代後半から増える病気なのか」といった疑問が生まれる方も多いのではないでしょうか。
今回は子宮体がんの基本知識や症状・検査法・予防について、わかりやすくお伝えしていきます。
子宮体がんとは?
子宮体がんは、子宮の内側を覆っている「子宮内膜(しきゅうないまく)」という粘膜から発生するがんです。
子宮は赤ちゃんを育てる場所として知られていますが、その内側の壁にあたる部分が子宮内膜で、ここががん化するのが子宮体がんです。
よく聞く「子宮頸がん(しきゅうけいがん)」とは発生する場所が異なります。
子宮頸がんは子宮の入り口付近にできるのに対し、子宮体がんは子宮の奥の部分に発生します。
原因やかかりやすい年齢層も違うため、それぞれ別の病気として理解しておくことが大切です。
子宮体がんは特に40〜50代の女性に多く見られます。
これは閉経前後のホルモンバランスの変化が大きく関わっているためです。
女性ホルモンの一つである「エストロゲン」が子宮内膜を厚くするはたらきを持っており、このバランスが崩れると子宮内膜が過剰に増殖してがん化のリスクが高まります。
また、食生活の欧米化や運動不足などの生活習慣も影響しているといわれています。
最近では、30代以下の若い女性にも子宮体がんが増えているという報告があります。
肥満やホルモンバランスの乱れ、ストレスなどが背景にあると考えられており、年齢に関わらず注意が必要です。
子宮体がんの主な症状

最も多いのは「不正出血」
子宮体がんで最も代表的な症状が「不正出血」です。
これは生理以外のタイミングで性器から出血することを指します。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
- 生理と生理の間に出血がある
- 性行為の後に出血がある
- 閉経したはずなのに再び出血がある
特に閉経後の出血は、子宮体がんの重要なサインとされています。
「もう閉経したから生理はこないはず」という時期に出血があった場合は、たとえ少量であっても早めに婦人科を受診することをおすすめします。
また、出血が数日続く、何度も繰り返すといった場合も見逃さないようにしましょう。
おりものの異常や下腹部の違和感
出血以外にも、おりものに変化があらわれることがあります。
子宮体がんが進行すると、次のような症状が見られることがあります。
- 茶色っぽいおりもの
- ピンク色や血が混じったようなおりもの
- 水っぽくサラサラしたおりもの
- 普段と違う生臭いにおいがする
これらの症状に加えて、下腹部に鈍い痛みや張ったような違和感を覚える方もいます。
「なんとなくお腹が重い」「生理痛とは違う痛みがある」といった感覚が続く場合は注意が必要です。
進行すると現れる全身症状
がんがさらに進行すると、子宮だけでなく体全体に影響が及ぶことがあります。
以下のような症状が現れる場合は、病気が進んでいる可能性があります。
- 貧血によるめまいや立ちくらみ
- 理由のない体重減少
- だるさや疲れやすさ(倦怠感)
- 骨盤周辺の痛みや腰痛
- 足のむくみ
これらの症状は他の病気でも起こりうるものですが、複数が同時に現れる場合や長く続く場合は、必ず医療機関で相談しましょう。
子宮体がんの初期症状と他の病気との違い
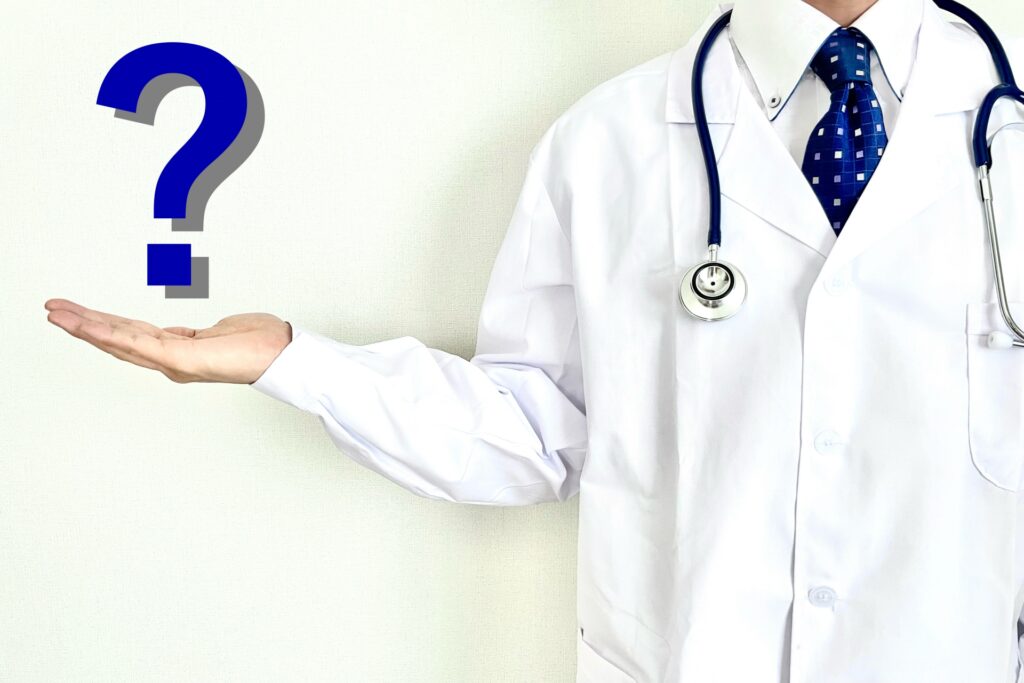
生理不順や子宮筋腫との見分け方
不正出血があると「更年期だから仕方ない」「生理不順だろう」と思い込んでしまう方も少なくありません。
しかし、不正出血は必ずしも更年期の症状とは限りません。
子宮体がんの初期症状である可能性もあるため、自己判断は危険です。
子宮筋腫(しきゅうきんしゅ)という良性の腫瘍でも不正出血が起こることがありますが、子宮体がんとは出血のパターンや量、期間が異なる場合があります。
例えば、子宮筋腫では生理の量が多くなる傾向がありますが、子宮体がんでは少量の出血がダラダラと続くことが多いです。
ただし、症状だけで病気を見分けることは難しいため、不正出血があった場合は必ず婦人科で検査を受けることが大切です。
「これくらいなら大丈夫」と放置せず、早めに専門医に相談しましょう。
初期段階では無症状のことも
子宮体がんの初期段階では、自覚症状がほとんどない場合もあります。
定期的な婦人科検診や超音波検査(エコー検査)を受けた際に、偶然見つかるケースも珍しくありません。
症状が出てから受診するのではなく、定期的に検診を受けることで早期発見につながります。
特に40代以降の方や、リスク要因に当てはまる方は、年に一度は婦人科検診を受けることをおすすめします。
子宮体がんの主な原因とリスク要因

子宮体がんの発生には、いくつかの要因が関わっているといわれています。
最も大きな影響を与えるのが、女性ホルモンの一つである「エストロゲン」です。
エストロゲンは子宮内膜を厚くする働きがあり、このホルモンが長期間過剰に作用すると、子宮内膜が異常に増殖してがん化のリスクが高まります。
また、肥満や糖尿病もリスク要因の一つです。
脂肪組織はエストロゲンを作り出すため、肥満の方は体内のエストロゲン量が増えやすく、子宮体がんのリスクが上がります。
糖尿病も同様に、ホルモンバランスや代謝に影響を与えることが知られています。
その他、以下のような要因もリスクを高めるといわれています。
- 出産経験がない(未経産)
- 閉経が遅い(55歳以降)
- 長期間のホルモン補充療法を受けた経験
- 家族に子宮体がんや大腸がんの人がいる(遺伝的要因)
これらに当てはまる方は、特に注意して定期検診を受けることが大切です。
子宮体がんが疑われるときの検査方法

子宮内膜細胞診・組織診
子宮体がんの診断では、「子宮内膜細胞診(さいぼうしん)」や「組織診(そしきしん)」という検査が行われます。
これは子宮内膜の細胞や組織を採取して、顕微鏡でがん細胞がないか調べる検査です。
検査は婦人科の診察台で行われ、細い器具を子宮の中に入れて細胞を採取します。
多少の痛みや違和感を感じることもありますが、数分で終わる検査です。
検査後に軽い出血や下腹部痛が起こることもありますが、通常は数日で治まります。
結果が出るまでには1〜2週間程度かかることが一般的です。
この間は不安に感じるかもしれませんが、早期発見のためには必要な検査ですので、医師の指示に従って受診しましょう。
経膣超音波検査・MRI・CT
子宮内膜の厚さを確認したり、がんの広がりや深さを調べるために、「経膣超音波検査(けいちつちょうおんぱけんさ)」や「MRI」「CT」といった画像検査が行われることもあります。
経膣超音波検査は、細長い器具を膣の中に入れて子宮の状態を観察する検査で、痛みはほとんどありません。
MRIやCTは体の断面を詳しく撮影できる検査で、がんがどこまで広がっているか、リンパ節や他の臓器に転移していないかを確認するのに役立ちます。
早期発見のためには、年に一度の婦人科検診を目安に、定期的に検査を受けることが大切です。
子宮体がんの治療法と予後

手術による摘出治療
子宮体がんの治療は、基本的に手術で子宮を摘出する方法が中心となります。
がんの進行度によって、子宮だけでなく卵巣や卵管、リンパ節も一緒に取り除くことがあります。
早期に発見されたがんであれば、手術によって完全に取り除くことができ、再発のリスクも低くなります。
そのため、やはり早期発見が何よりも重要です。
ホルモン療法・放射線療法・抗がん剤治療
がんが再発した場合や、進行している場合には、ホルモン療法や放射線療法、抗がん剤治療が選択されることもあります。
ホルモン療法は、がん細胞の増殖に関わるホルモンの働きを抑える治療法です。
また、まだ妊娠を希望している若い女性の場合、条件が合えば子宮を残す治療法(ホルモン療法など)を選択できることもあります。
担当医とよく相談して、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。
日常生活でできる予防と早期発見のポイント

子宮体がんを完全に予防することは難しいですが、リスクを減らすために日常生活で心がけられることがいくつかあります。
まず、適正体重を維持することが大切です。
肥満はエストロゲンの過剰分泌につながるため、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。
特に野菜や果物を多く取り入れた食生活は、がん予防にも役立ちます。
そして何より重要なのが、定期的な婦人科検診を受けることです。
症状がなくても、年に一度は検診を受けることで、早期発見につながります。
特に閉経後に出血があった場合は、たとえ少量でも必ず婦人科を受診してください。
「恥ずかしい」「忙しい」と後回しにせず、自分の体を守るための行動を優先しましょう。
また、ホルモンバランスを整えるために、十分な睡眠やストレス管理も大切です。
規則正しい生活リズムを保ち、無理のない範囲で体を動かすことを習慣にしましょう。
まとめ

子宮体がんは、不正出血やおりものの異常といった症状が現れることが多いがんです。
特に閉経後の出血は重要なサインですので、見逃さずに早めに受診することが大切です。
初期段階では無症状のこともあるため、定期的な婦人科検診を受けることが早期発見の鍵となります。
40代以降の女性に多いがんですが、最近では若い世代にも増えているといわれています。
適正体重の維持やバランスの良い食生活、定期検診など、日頃からできる予防策を取り入れて、自分の体を大切にしていきましょう。
少しでも気になる症状があれば、ためらわずに婦人科を受診してくださいね。