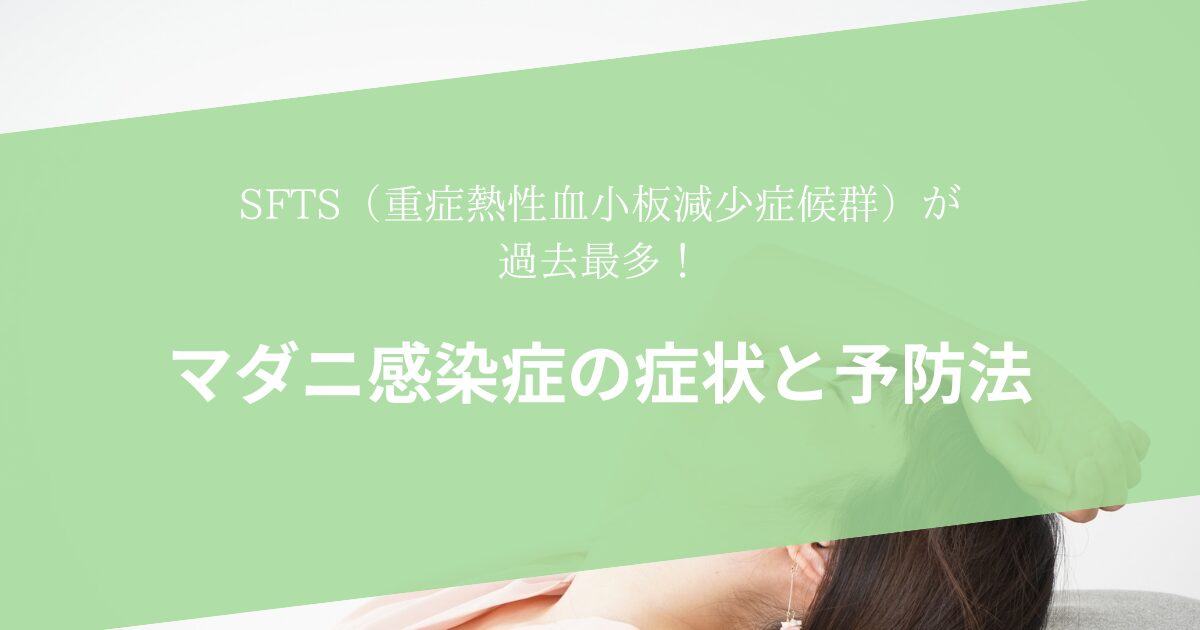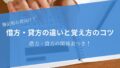2025年8月19日の報道で、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の感染者数が全国で過去最多となったことが伝えられました。
SFTSはマダニが媒介する感染症で、発熱や下痢などの症状から重症化し、死亡例も確認されています。
キャンプや庭作業など身近な場面でも感染リスクがある病気で、日頃からの対策がとても重要です。
本記事ではSFTSの特徴や初期症状、自分でできる予防策などについて解説していきます。
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは?マダニが媒介する感染症の基礎知識
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは、マダニにかまれることで感染するウイルス性の病気です。
発症すると高熱や消化器の不調がみられ、重症化すると命に関わることもあります。
なぜこの病気が危険かというと、特効薬やワクチンがなく、自然界のマダニを完全に避けることも難しいためです。
国内では毎年のように患者が報告されており、西日本を中心に発生が目立ちますが、最近では北海道でも確認されています。
つまり「どこにいても感染する可能性がある病気」として、理解しておく必要があるのです。
SFTSの潜伏期間は6日〜2週間
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、マダニにかまれてすぐに症状が出るわけではありません。
発症までには6日から2週間ほどの期間があり、このあいだは自覚症状がないのが特徴です。
体の中ではウイルスが少しずつ増えていても、外からは気づきにくい状態が続きます。
そのため、農作業や山歩きのあと、数日経ってから急に発熱や体調不良が出ることがあります。
SFTSの初期症状
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、初期から体に異変があらわれます。
体内に侵入したウイルスが全身に影響を及ぼすためです。
ここでは、代表的な初期症状4つについて詳しく解説していきます。
38℃以上の高熱
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)の初期には、38℃以上の高熱が出るケースが目立ちます。
体がウイルスと戦う過程で、急に体温が上昇するためです。
普段の風邪では微熱程度の人でも、この病気ではあっという間に39℃近くまで上がることがあります。
強い倦怠感や食欲不振を伴うこともあり、「ただの風邪」とは違うサインに気づける症状といえるでしょう。
倦怠感・脱力感
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)の初期には、強い倦怠感や全身の力が抜けるような脱力感がみられることが多いです。
体内でウイルスが増えることでエネルギーが消耗し、日常の動作さえ負担に感じるほど体が重だるくなります。
「立ち上がるのもつらい」「横になっても疲れがとれない」といった感覚を訴える人も少なくありません。
こうした症状は風邪や疲労とも似ていますが、SFTSではより強く、長く続く点が大きな違いです。
消化器症状
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)では、発熱と並んで消化器の不調が目立ちます。
これは、ウイルスが体内で炎症を引き起こすことで、胃腸が影響を受けやすくなるためです。
具体的には、吐き気や嘔吐、下痢、腹痛などが代表的で、食欲が急に落ちるケースも多く報告されています。
リンパ節の腫れ
体内でウイルスと免疫が戦う過程でリンパ節が反応し、首まわりや脇の下などのリンパ節に腫れがみられることがあります。
「しこりのように触れる」「片側だけ腫れている」といった症状がみられることも。
風邪でも似た症状が出る場合がありますが、SFTSでは発熱や倦怠感と一緒にあらわれるのが特徴です。
出血傾向
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)では、血を止めるはたらきを持つ血小板が減るため、わずかな刺激でも出血しやすくなります。
具体的には、歯みがき後に歯ぐきから血が出る、皮膚にあざのような紫斑(しはん)がみられる、便に血が混ざるといった症状がみられることがあります。
その他の初期症状
代表的な高熱や消化器症状以外にも、次のような不調が出ることがあります。
- 頭痛
- 筋肉痛・関節痛
- めまい・ふらつき
- 寒気
一見すると風邪や疲労とも似ていますが、SFTSでは複数の症状が同時に出ることが多いのが特徴です。
マダニ感染症を防ごう!服装・虫よけ・受診の目安
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、マダニに刺されないことが最大の予防になります。
服装の工夫や虫よけスプレーの活用、帰宅後のチェックを徹底することで、感染リスクを大きく減らせます。
自分でできる対策を知り、日常生活に取り入れていきましょう。
屋外では肌の露出を極力減らす服装を
マダニは草むらや山林に潜み、人の肌に取り付くことで感染を広げます。
そのため屋外活動では、肌の露出を避ける工夫が欠かせません。
長袖・長ズボンを着用し、手首や足首までしっかり覆うと安心です。
シャツの裾をズボンに入れたり、ズボンの裾を靴下に入れたりすることで、服の隙間からマダニが侵入するのを防げます。
さらに、明るい色の服を選べば、マダニが付着した際に見つけやすいという利点もあります。
虫よけ成分「DEET/イカリジン」のスプレーを併用
衣服で肌を覆っていても、マダニは隙間から侵入してくることがあります。
そこで役立つのが、虫よけ成分として知られるDEET(ディート)やイカリジンを含むスプレーです。
衣服や靴の上から吹きかけると効果が持続し、マダニが近づきにくくなります。
市販の製品には、子どもでも使える低濃度タイプもあるため、年齢や使用シーンに合わせて選べるのも安心◎
服装対策と組み合わせることで、より予防効果が高まります。
野外活動後はシャワーを浴びて、全身を入念にチェック
草むらや山林から帰ったあとに大切なのが、マダニが付着していないかどうかの確認です。
シャワーで汗や汚れを洗い流すと同時に、鏡を使って全身をチェックしましょう。
首や耳の後ろ、わきの下、膝の裏、足の付け根などはマダニが隠れやすい部位なので特に注意が必要です。
また、衣服や持ち物に付いている場合もあるため、帰宅後にまとめて確認しておきましょう。
こうしたひと手間をかけることで、感染のリスクを大きく減らせます。
ペットのマダニ対策も忘れずに
散歩や庭遊びのあと、毛に隠れたマダニが家の中に持ち込まれることも少なくありません。
特に耳のまわりや首筋、足の付け根などはマダニが付着しやすい部位です。
体をなでながらチェックしたり、異変があれば動物病院で相談してみましょう。
マダニに刺されたら、自己処理はNG!速やかに医療機関へ
マダニは強く皮膚に食い込む習性があり、無理に取ろうとすると余計に深く刺さることも。
もし刺された場合は、そのままの状態で皮膚科などの医療機関を受診するのがおすすめです。
早めに専門家に処置してもらうことで、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などの感染症のリスクを減らせます。
まとめ|マダニに刺されたら、すぐに医療機関へ!
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、マダニを介して感染する危険な病気です。
発熱や下痢、強い倦怠感から重症化し、命に関わることもあります。
現在は特効薬やワクチンがないため、日常の予防が最大の対策です。
屋外活動では長袖・長ズボンの着用や虫よけスプレーが基本。
帰宅後は全身のチェックを忘れずに。
さらに、ペットのマダニ対策や、かまれた際の早めの受診も欠かせません。
日々の心がけでリスクを減らし、安心してアウトドア活動を楽しみましょう!