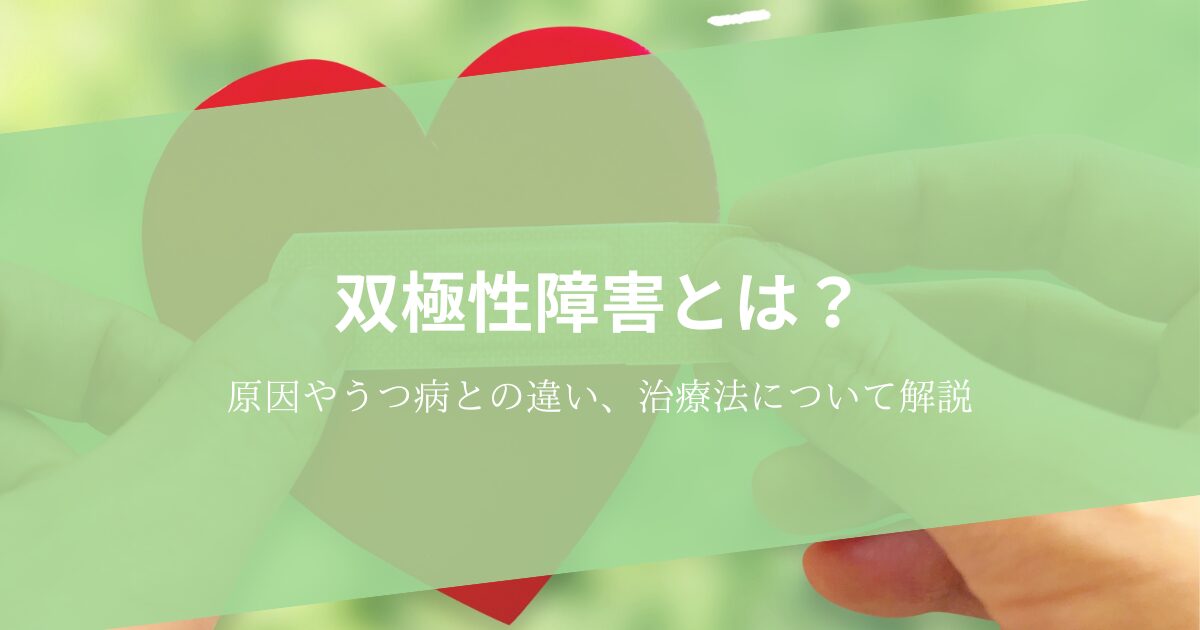気分が落ち込んで何も手につかない日もあれば、反対にエネルギーがあふれて眠れない程活動的になる、そんな気分の波に悩まされるのが「双極性障害」です。
一見うつ病と似ていますが、躁状態と呼ばれる「気分が高ぶる時期」がある点で異なります。
本人が気付きにくいことも多く、周囲からの理解も得られにくいため、早期の受診と適切な治療が大切です。
この記事では、双極性障害の特徴や原因、うつ病との違い、主な治療法までをわかりやすく解説していきます。
双極性障害とは?
双極性障害は、気分の波が激しくなる精神疾患で、うつ状態と躁状態を繰り返すことが特徴です。
気分が沈んで何もやる気が出ない時期と、逆に気分が高ぶり活動的になりすぎる時期が交互に訪れることで、日常生活や人間関係に大きな影響を与えることがあります。
例えば、ある日は憂うつで動けなかったのに、翌週には突然多弁でハイテンションになるなど、極端な気分の変化がみられます。
こうした症状は本人も気付きにくく、周囲からも理解されづらいため、早期の診断と治療が大切です。
双極性障害は、適切な治療とサポートがあれば、安定した生活を送ることも十分に可能です。
双極性障害とうつ病との違い
双極性障害とうつ病はどちらも気分障害に分類されますが、症状のあらわれ方に大きな違いがあります。
双極性障害では気分が落ち込む時期に加えて、テンションが異常に高くなったり、活動的になりすぎたりする時期が交互にあらわれます。
一方で、うつ病は気分の低下が中心で、躁状態のような高揚感はみられません。
気分の波があるかどうかが両者を見分けるカギになるため、違和感を覚えたときは、早めに専門の医師に相談することが大切です。
双極性障害の主な症状|躁・うつの特徴
双極性障害では、気分の波が大きく変動します。
ここでは、躁状態とうつ状態、それぞれの特徴的な症状について詳しく解説します。
躁状態の主な症状
躁状態では、気分が高まりすぎて活動的になり、日常生活に支障をきたすことがあります。
睡眠時間が減っても元気に動き回ったり、話し続けて止まらなかったりするのが典型的な症状です。
自信過剰や浪費、衝動的な行動が目立つこともあり、本人は好調だと感じているケースが多いのも特徴です。
うつ状態の主な症状
うつ状態では、気分が落ち込み「何をしても楽しく感じられない状態」が多くなります。
疲れやすさや集中力の低下、不眠や過眠、食欲の変化などもよくみられる症状です。
自分を責める思考が強くなり、将来に希望がもてなくなるケースもあります。
双極性障害の原因
双極性障害の原因は一つではなく、遺伝や脳の働き、ストレスなど複数の要因が関係していると考えられています。
遺伝的要因
家族や親族に同じ病気を持つ人がいる場合、発症リスクが高まることがわかっています。
両親のいずれかが双極性障害の場合、子どもも発症する確率が、一般より高くなる傾向があります。
ただし、遺伝的要因があるからといって必ず発症するわけではなく、環境やストレスなど、ほかの要因とも組み合わさって影響し合っています。
脳内の神経伝達物質の異常
双極性障害は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることで発症すると考えられています。
特にセロトニンやドーパミン、ノルアドレナリンなどのはたらきが乱れると、気分のコントロールに支障をきたすことがあります。
躁状態ではドーパミンの活動が過剰になり、うつ状態では不足する傾向がみられるのが特徴です。
こうした神経の働きの乱れには、薬物療法が効果的とされています。
ストレスや生活環境
強いストレスや不安定な生活環境は、双極性障害の発症や悪化の引き金になることがあります。
なかでも、人間関係のトラブルや仕事のプレッシャー、ライフイベントによる変化などが影響しやすいとされています。
過労や引っ越し、出産なども精神的な負荷となり、気分の波を引き起こすきっかけになることも。
ストレスをため込まず、心身のバランスを保つ工夫が、双極性障害の発症予防にもつながります。
ホルモンバランスの変化
ホルモンバランスの乱れも、双極性障害の発症に関係すると考えられています。
特に、甲状腺ホルモンや性ホルモンの変動は、気分や睡眠、体調に大きな影響を与えることがあります。
体と心のリズムは密接に関係しているため、体調の変化にも注意を向けることが大切です。
性格傾向や気質
双極性障害の発症には、性格や気質も関係しているといわれています。
特に、完璧主義で責任感が強い人や、感受性が豊かな人はストレスの影響を受けやすく、気分の波が大きくなりがちです。
また、周囲に気を遣いすぎたり、自分を追い込みやすいタイプの人は、心に疲れをため込みやすい傾向にあります。
こうした性格的な特徴は、直接の原因とはいえないものの、発症リスクを高める一因とされています。
双極性障害の主な治療法
薬物療法
気分安定薬
双極性障害の治療で中心となるのが、気分安定薬です。
躁状態とうつ状態の波を抑え、再発を予防する効果があります。
代表的な薬にはリチウムやバルプロ酸、ラモトリギンなどがあり、症状や体質に応じて処方されます。
薬の効果を最大限活かすためには、自己判断での中断や量の調整は避け、医師の指示を守って服用することが大切です。
抗精神病薬
双極性障害の躁状態が強い場合には、抗精神病薬が使用されることもあります。
気分の高揚や興奮、衝動的な行動を抑える効果があり、急性期の症状を安定させるのに役立ちます。
オランザピンやクエチアピン、アリピプラゾールなどが代表的な薬です。
抗うつ薬
双極性障害のうつ状態には、抗うつ薬が使われることもあります。
主にSSRIやSNRIなどが用いられ、気分の落ち込みや意欲の低下にはたらきかけます。
使用中は気分の変化に注意し、必ず医師と相談しながら治療を進めましょう。
心理療法
認知行動療法(CBT)
双極性障害の治療では、薬物療法に加えて認知行動療法(CBT)が有効とされています。
思考や行動のクセを見直すことで、気分の波を穏やかにし、再発リスクの軽減につなげます。
具体的には、「うまくいかない=自分のせい」といった極端な考え方に気付き、柔軟なとらえ方へ変えていく練習などを行います。
ストレスへの対処法を身につけることができるため、日常生活の安定にも役立つ治療法です。
対人関係療法
対人関係療法は、人間関係に起因するストレスや感情の問題に焦点を当て、双極性障害の症状を改善していく心理療法です。
対人関係のトラブルや役割の変化が気分の波に影響することがあるため、関係性の見直しやコミュニケーションの工夫が重要になります。
家族や職場との関係に悩みがある場合、そのやりとりを整理し、より良い対応方法を学んでいきます。
安定した人間関係は、症状の再発予防にもつながります。
家族療法
双極性障害の治療では、家族の理解と協力も重要です。
家族療法では、病気への正しい知識を共有し、接し方やサポート方法を学びます。
具体的には、気分の変動にどう対応するか、本人のサインをどう見極めるか、などを話し合う機会がもたれます。
家族が安心して支えられる環境をつくることで、本人の安定した生活にもつながり、再発防止にも役立ちます。
生活習慣の見直し
双極性障害の安定には、生活習慣の整え方が大きく影響します。
特に、睡眠リズムの乱れは、気分の波を悪化させる要因となりやすいため注意が必要です。
毎日同じ時間に寝起きする、過度な刺激を避けてリラックスするなど、小さな工夫が心の安定につながるでしょう。
まとめ
双極性障害は、気分の波が大きく変動するこころの病気であり、正しい理解と適切な治療が大切です。
うつ病との違いや症状の特徴、原因、治療法などを知ることで、本人も周囲もより前向きに向き合うことができるでしょう。
薬物療法に加え、心理療法や生活習慣の見直しを取り入れることで、安定した日常を取り戻すことは十分に可能です。
一人で抱え込まず、専門家や家族と連携しながら、無理のないペースで回復を目指していきましょう。